給料はなぜ物価に追いつかないのか
前編はこちら→【前編】本当に物価よりも給料の伸びを上げられるの?(政治家が語らない、日本経済の物価上昇と給与の関係を読み解く)
😏 私
財布の中を覗くと、いつの間にか小銭が消え、札はあっという間に薄紙のように頼りなくなる。
ニュースでは「賃上げ」「インフレ」の四字が踊り、人々は希望のような不安のような顔をしている。
だが、どうして給料は物価に追いつかないのか。
なぜ企業は昇給を渋りながら、昼休みのパンだけは値上げしてくるのか。
ここらで一度、経済という魔法のトリックを見破ってみたい。
給与を伸ばすには「生産性」が鍵
💬 ランディ君
給与を物価上昇より高いペースで伸ばすには、生産性の向上が不可欠です。
例えば、2人で2個作っていた商品を1人で2個作るようになれば、原価に含まれる人件費は半分になります。
単純計算で給与を倍にすることも可能です。
つまり「同じ時間でより多くの成果を出す」ことが昇給の前提になります。
😏 私
なるほど。魔法ではなく算数の世界だな。
2人でせっせと握っていたおにぎりを、ある日突然1人で握り切れるようになったら、確かに経営者はニヤリと笑い、労働者のポケットも多少膨らむかもしれない。
だが、それは筋肉と根性で解決してきた過去の日本の得意技ではなかったか。
デフレ時代の賃金停滞とサービス残業
💬 ランディ君
はい。日本は長らくデフレ環境にありました。
売価を上げられないため、企業は「勤務時間を増やす」ことで原価を下げてきました。
その象徴がサービス残業や無理なノルマです。
労働生産性を上げるのではなく、労働時間を延ばす方向に頼ってきたわけです(出典:OECD Productivity Data)。
😏 私
ああ、思い出した。
深夜のオフィスに灯る蛍光灯、疲れ果てた顔でカップ麺をすすりながら「俺たちの頑張りが日本を支えてる」と言い聞かせた時代。
実際は自分の寿命を原価に組み込んでいただけかもしれん。
だが今や、そんな「従業員根性モデル」はもはや通用しない。
人手不足、価値観の多様化、誰も無償奉仕など引き受けてくれぬ。
生産効率の限界と中小企業の苦悩
💬 ランディ君
その通りです。しかも、生産効率の向上はすでに限界に近づいています。
機械化や組織の合理化は高度経済成長期から進められてきました。
今後、飛躍的に効率が上がる可能性は低いと考えられます(出典:内閣府 経済財政白書2024)。
😏 私
つまり、工場にロボットを並べ、書類をクラウドに飛ばしても、もう「魔法の効率化」は残っていない。
そもそも資金も人材も限られる中小企業にとって、生産効率の向上など「言うは易し行うは難し」そのものだ。
経営者が「効率化だ!」と叫んでも、現場は古びた機械と少ない人手でヒイヒイ言うのが現実だ。
政治の役割と必要なビジョン
💬 ランディ君
この問題は単純な企業努力の枠を超えています。
産業構造の変化、国際競争力の低下、国内需要の伸び悩みなどが複雑に絡み合っています。
減税や給付金は一時的な支援にはなりますが、根本的な解決にはつながりません(出典:IMF 日本国別審査2024)。
😏 私
そうだろう。給付金は一瞬で消える花火のようなものだ。
打ち上げている間は夜空が明るいが、煙が消えたら暗闇は戻る。
問題は、その暗闇を照らす長期的な灯りを誰が用意するかだ。
企業は体力勝負で限界に近い。
ならば、政治家にはぜひとも「大風呂敷」ではなく、現実に役立つビジョンを示してほしい。
口当たりの良いスローガンではなく、現場が動ける地図を描いてほしい。
まとめ
💬 ランディ君
- 給与が物価を上回るには、生産性向上が不可欠です。
- デフレ時代は「長時間労働」に頼る形で原価を下げてきました。
- 今後は従業員の自己犠牲モデルは通用しません。
- 生産効率の大幅な改善は困難であり、中小企業には特に厳しい課題です。
- 問題は産業構造や国際競争力に根差しており、減税や給付金は一時的効果しかありません。
- 政治には具体的な長期ビジョンが求められます。
😏 私
要するに、給料と物価の綱引きは単なる数字合わせではない。私たちの働き方、企業の姿勢、そして国家の構想力、そのすべてが関わる大仕事なのだ。机上の計算では簡単に倍になる給与も、現実には多くの壁がある。とはいえ、壁があるなら叩いて音を確かめ、時に穴を開けてみるのも人間の知恵だ

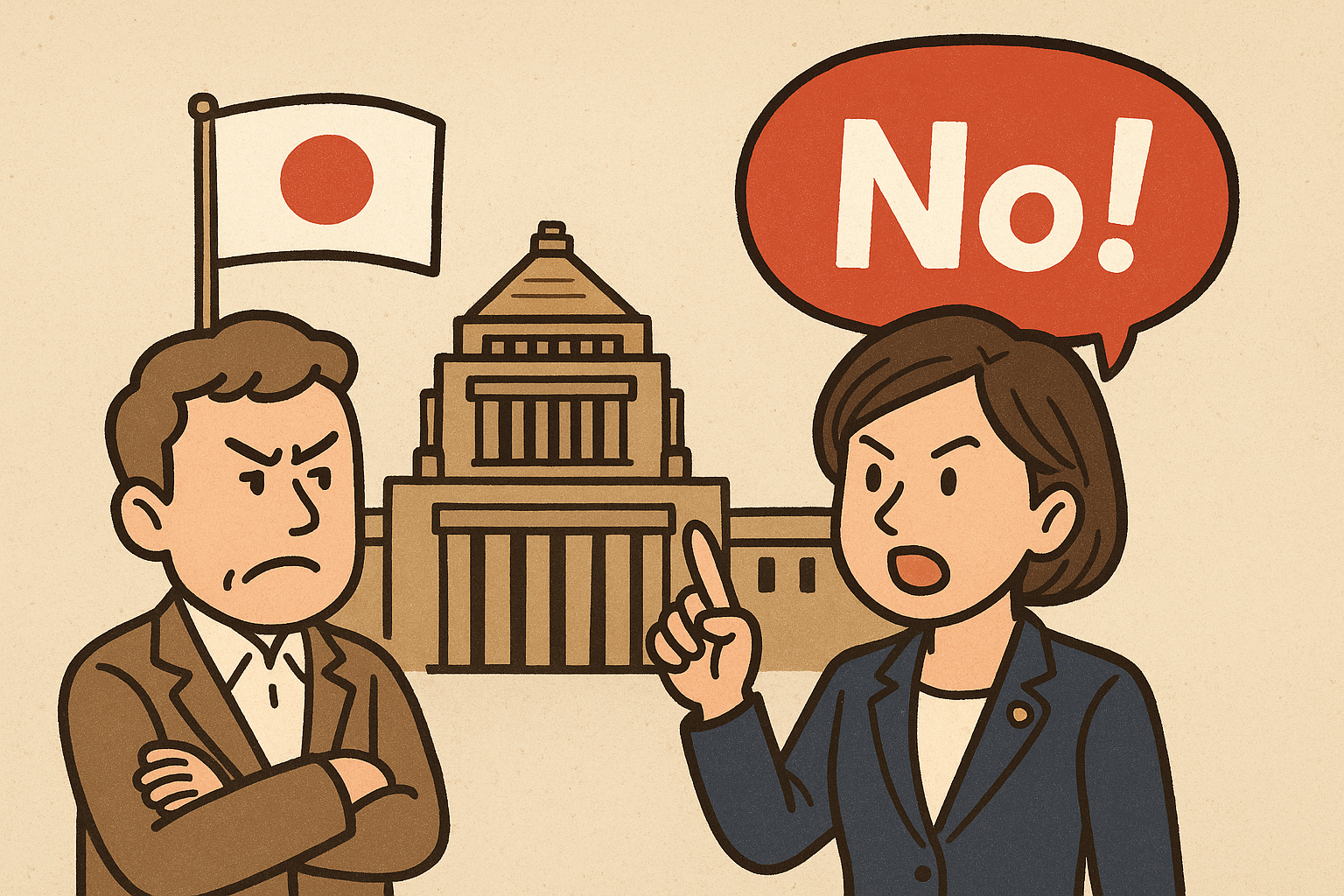
コメント