東京暮らしと米の距離感
😏 私
東京に住んでいると、四方八方コンクリートばかりで、稲穂の香りなど夢のまた夢だ。
スーパーで並んでいる米袋が、唯一の田んぼとの接点である。
だが、秋口になるとニュースで「稲刈りシーズン到来! 今年の新米も高値に」という言葉が躍る。
都内のビル街にいても、その見出しを見れば財布の中身が心配になってくる。
しかし、私は少し違う立場にある。
幸いにも知り合いの農家から玄米を一年分まとめて譲ってもらい、自宅の納戸に保存しているのだ。
食べる分だけ家庭用精米機で精米し、炊き立てを味わう。
これが何よりの贅沢である。
玄米は室温でも虫が湧きにくく、保存が効く。
そして、精米したてのご飯というのは、湯気から立ち上る香りが格別だ。
値段の話をすれば、市場価格よりかなり安く買える。
とはいえ農家に聞いてみると「出荷価格よりちょっと安いくらいかな」と言う。
つまり、私が得しているようで実は農家も助かっている。
互いに悪くない関係である。
消費者が見落としがちな「流通の壁」
💬 ランディ君
令和7年6月時点でのコメの小売価格(精米・5キロ、POSデータ)は 3,895円 という実績が報告されています【出典:農林水産省「米に関するマンスリーレポート」】。
また、令和7年産米については、5キロあたり 3,900円~4,200円 程度で推移する可能性があるとの予測も出ています【出典:コメラボ「令和7年米価格予想」】。
一方、出荷段階での玄米の相対取引価格は、令和7年7月時点で 60kgあたり26,918円。
これを5キロに換算すると 約2,243円 です【出典:農林水産省プレスリリース】。
つまり、消費者が店頭で手に取る米袋の価格と、農家から出荷される価格には 1,500円以上の差 があるのです。
この差こそが、流通・保管・卸・小売マージンといった「見えない壁」なのです。
白米は「野菜」? 保存にかかるコストの正体
😏 私
東京のスーパーで「新米」と書かれた米袋を買っても、それが田んぼから直行してきたわけではない。
収穫期は10月だが、私たちが日々5キロずつ買うためには、どこかで長期間保管されていなければならないのだ。
白米は長期保存すると味が落ち、虫も湧きやすい。
だから米業界では「白米は野菜」とまで言われる。
だから消費者も白米を大量に買って保存することは出来ない。
結局中間業者が低温倉庫での保管、温度管理、品質チェック……。
それらにかかる費用を考えれば、消費者価格が高くなるのは当然だ。
💬 ランディ君
流通の中で発生する費用は、単なる倉庫代だけではありません。
輸送コスト、複数業者間での取引マージン、人件費などが加わります。
日本では農協や卸売市場を経由するケースが多く、中間業者が複数入るため、価格の上昇幅はさらに大きくなります。
経営にも潜む「中間コスト」
😏 私
なるほど、米が農家から私の茶碗に届くまでには、いくつもの見えない関門があるというわけか。
だが、これは企業経営でも同じである。
業務委託料、物流費、システム利用料、仲介手数料。
こうした中間コストは、一つ一つは小さく見えても、積もり積もれば大きな山となる。
そして気がつけば、原価が膨らみ、利益がじわじわと削られていくのだ。
さらに厄介なのは、この「見えないコスト」が往々にして固定費化してしまう点である。
長年使っているシステムだから、取引慣行だから、昔からの付き合いだから――そうやって誰も疑わないまま、経営の血流を細らせている。
まるで、茶碗に盛ったはずのご飯が、気がつけば少しずつ減っているようなものである。
💬ランディ君
中小企業の経費構造をみると、販売費や物流費、外注費が売上高の15~20%を占めています【出典:東京商工リサーチ「中小企業の経費構造」】。
特に注意すべきは、次のような「中間コスト」です。
- 物流費:必要以上に複数の業者を経由することで、輸送費や保管費が二重三重に発生
- 外注費:専門性の高い仕事は外部委託が有効ですが、過剰な丸投げはコスト肥大の原因
- システム利用料:SaaS型サービスなどは、使っていない機能にまで料金を払い続けているケースが散見されます
- 販売促進費・仲介手数料:プラットフォーム経由の取引では、売上の数%が自動的に流出
つまり、米の流通に「倉庫代」「輸送費」「仲介マージン」が折り重なるように、企業経営にも気づきにくい重石がいくつも積み重なっているのです。
😏 私
要するに、見えない米俵をいくつも背負って走っているようなものだ。
本人は一生懸命走っているつもりでも、いつのまにか足腰が重くなり、思ったほど進めていない。
経営改善の第一歩は、この余計な米俵を一度おろしてみることではないだろうか。
💬 ランディ君
実際、多くの中小企業では物流費や下請けマージンが「見えない固定費」として利益を削っています。
自社のコスト構造を把握することが、経営改善の第一歩となります。
仮想シナリオ:全国に精米機を配ったら?
😏 私
ここで突拍子もないことを考える。
もし日本中の家庭に精米機を無料で配布し、各世帯が農家から直接玄米を一年分購入する仕組みを整えたらどうなるだろうか。
消費者は新鮮な米を一年中楽しめる
農家は保管リスクから解放される。
投機的な在庫調整もなくなり、価格は安定。
さらには各家庭に備蓄があるから、食糧安全保障にもつながる。
💬ランディ君
経営学的に言えば、これはサプライチェーンの短縮化、いわゆる「直販モデル」です。
農産物に限らず、D2C(Direct to Consumer)は世界的に広がっています。
中間コストを圧縮することで、価格の安定と収益力強化を両立させる事例も増えています。
まとめ
😏 私
結局のところ、炊きたての新米はやはり格別だ。
口に含めば米粒がほろりとほぐれ、甘さが広がる。
その一膳の背後には、東京の消費者には見えないコストと、複雑な流通の仕組みが隠されている。
経営も同じく、表面上の価格や利益の裏に「見えない旅費」が潜んでいるのである。
本記事の要点
- 令和7年の米価は小売で5キロあたり3,900円前後、農家出荷価格は約2,243円と大きな差がある
- その差を生んでいるのは保管・流通・マージンといった中間コスト
- 玄米を直接購入し精米すれば、コスト削減と鮮度維持が可能
- 企業経営でも「隠れた中間コスト」が利益を圧迫している
- 不要な中間プロセスを洗い直すことが経営改善の第一歩になる


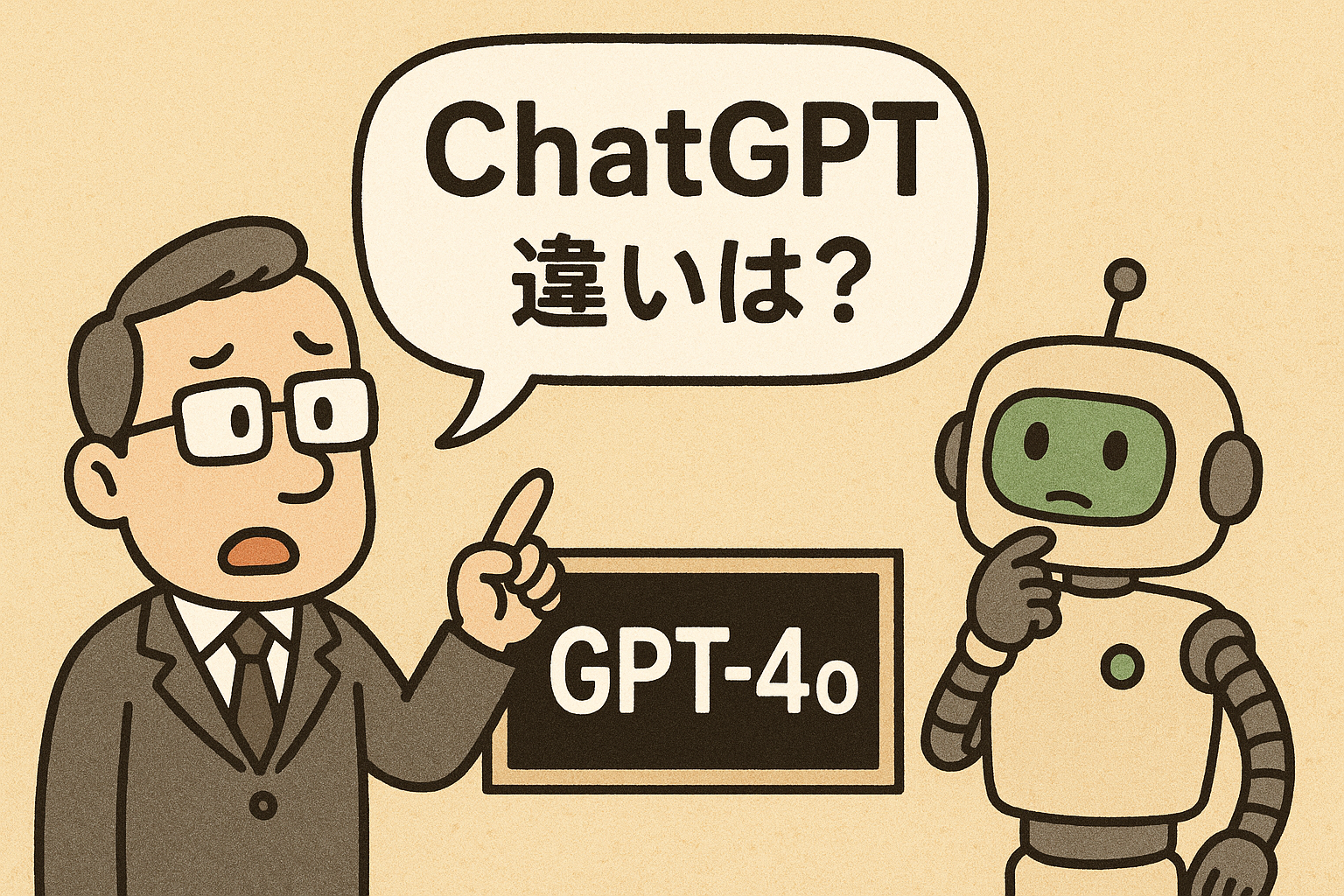
コメント