ChatGPTが誤る理由
前編はこちら→【前編】ChatGPT無料版と有料版の違いって何?(間違いはここから始まった)
😏 私
それにしても、AIはどうしてあんなに堂々と間違えるのだろうか。
まるで胸を張って「これが正解です」と言い切ったあとで、あっさり「すみません、先ほどの説明は誤りでした」と訂正する。
人間なら赤面ものだが、AIは顔色ひとつ変えない。
実に羨ましい胆力である。
💬 ランディ君
主な理由は次のとおりです。
最新情報の反映が追いつかない
学習データには時間的な限界があります。
特に直近の出来事や新しい制度などは、まだ情報に反映されていない場合があります。
数字や統計を“それっぽく”補ってしまう
AIは穴を埋めるのが得意です。
そのため、正確な数字がないときに「ありそうな数値」を提示してしまうことがあります。
質問があいまいで解釈が揺れる
人間同士でも「え、それってどういう意味?」となる場面は多いです。
AIも同じで、曖昧な質問は複数の解釈を生み、回答がぶれる原因になります。
UI表示と実際のモデルに差がある
画面に「GPT-5」と表示されても、裏で動いているのは別モデルという場合があります。
技術的な仕組みとUI表示が一致しないことは珍しくありません。
😏 私
なるほど。つまり「それっぽい答え」を整えて返す癖があるのだな。
まるで居酒屋で、隣の席の人が得意げに語る「俺の経済予測」と同じだ。
妙に筋は通っているのだが、翌日新聞を見ると見事に外れている。
AIの堂々たる態度は、その再現芸に近い。
質問のコツ
😏 私
では、どうすれば正しい答えを引き出せるのか。
AIに「煙に巻かれた説教」をさせず、実務に役立つ回答をもらうにはどうしたらよいのだろう。
💬 ランディ君
以下の工夫がおすすめです。
日時を明確にする
例:「2025年9月1日時点では?」と具体的に聞くと、回答が時系列に即して整理されます。
質問を分解する
「無料版のモデルは?」「利用制限は?」のように分けると、誤解を減らせます。
数値や統計は出典を確認する
「その数字の出典は?」と尋ねるだけで、回答の信頼度がぐっと高まります。
公式サイトやURLを添えるよう促す
AIは参照先を挙げられるので、URL付きの回答を求めると安心です。
あいまいな言葉は避ける
「最近」「だいたい」といった表現は解釈が広がり、回答が不安定になります。
😏 私
特に数字に関しては油断禁物だ。裏付けがなければ、経営判断に使うのは危うい。
AIの答えを鵜呑みにして「来期の売上予測」を決めたら、それこそ大惨事だ。
数字に関しては必ず「二本足で立っている」か確認する必要がある。
中小企業経営での活用視点
😏 私
実務に落とし込むならこうだ。
文案や議事録の下書きは大いに活用できる
スピードが求められるメールや議事録では、AIの力は非常に便利だ。
数値やデータ分析は必ず出典をチェック
補助金、助成金、税制などは間違えると致命傷になる。
公式リンクで裏取りをするのが鉄則だ。
複数モデルで比べる
同じ質問を複数回投げてみると、答えの「癖」が見える。
人間の社員だって二人に聞けば違う答えが返るのと同じことだ。
💬 ランディ君
つまり、「素早さ」と「正確さ」を切り分けることです。
草稿づくりはAIに任せ、最終判断は人間が出典を見て確認する。
これが中小企業における安全な使い方といえます。
後編まとめ
💬 ランディ君
注意点を整理します。
- 質問は具体的に、時点を明確に
- 数字や統計は必ず出典を確認
- 表示モデル名と実際のモデルは違うことがある
- 複雑な質問は分解して短く
- 公式情報をチェックする習慣を持つ
😏 私
AIの間違いは、我々が正しい質問を学ぶきっかけになる。結局は「どう使うか」がすべてなのだ。AIに怒鳴っても無駄だが、正しい問いを立てれば、想像以上の助手となってくれる。
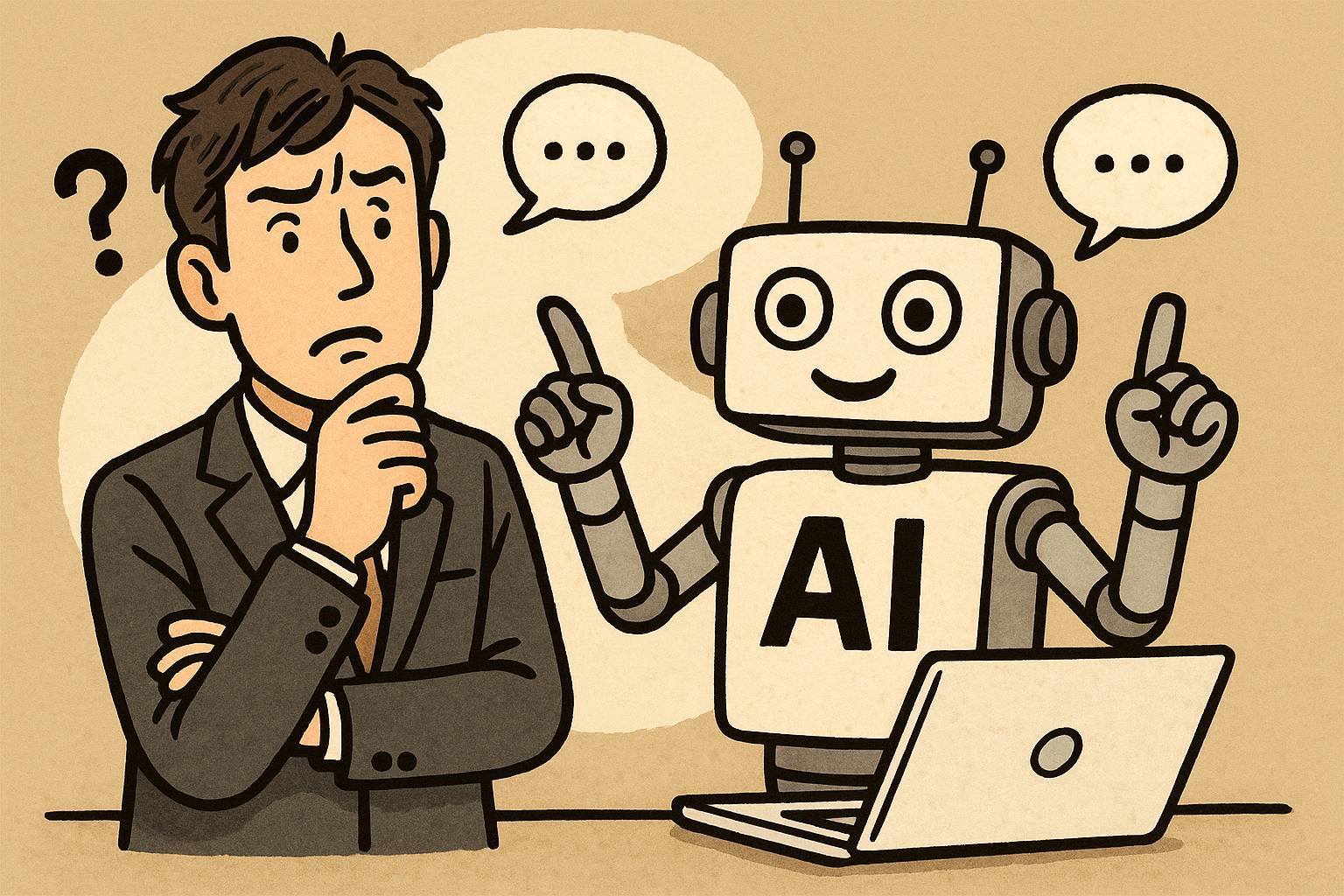


コメント