序章:万博に漂うお金の匂い
😏 私
これまで私は大阪・関西万博に対して、暑いだの、行列が長いだのと愚痴ばかりこぼしてきた。
しかし今回はひとつ真面目に、コンサルタントの視点から “お金の匂い” を追ってみたいと思う。
万博のパビリオンを歩いていると、そこに潜む経済学的な構造が透けて見えてくるから面白い。
万博はイメージ戦略の見本市
💬 ランディ君
万博は “イメージ戦略の見本市” と呼ばれることがあります。
大阪・関西万博でも150を超える国や地域、企業が参加し、それぞれ独自のパビリオンを建設しています。
建設費や運営費は数十億円規模に及ぶケースが多く、これは単なる展示会とは桁違いの投資です。
数十億円の投資をどう回収するか
😏 私
数十億円! この金額をどうやって回収するのかが、経営の眼鏡で覗くと最大の焦点となる。
パビリオンで入場料を直接稼げるわけでもないし、来場者に焼きそばを売って儲けるわけでもない。
つまり、狙うは “間接的な売上増”、要するにイメージアップである。
誰も彼もが同じ手を打つのだから、差別化は “どれだけ好印象を残せるか” にかかっているのだ。
民間パビリオンの必死さ
💬 ランディ君
民間企業のパビリオンは特に強い意識を持ちます。
建設や運営にかかるコストはほぼ自腹であり、株主への説明責任も存在します。
そのため投資回収を念頭に、来場者を楽しませつつ、自社ブランドを好意的に記憶してもらう仕組みを作り込みます。
😏 私
なるほど、だから彼らは必死なのだな。
自動車メーカーなら未来型モビリティを体験させ、製薬会社なら健康寿命を延ばす展示を見せる。
冷房を効かせて待ち時間を快適にするのも演出のひとつだ。
まるで株主総会のプレゼンテーションを延々と繰り広げているように見える。
過去の万博に学ぶ戦略
💬 ランディ君
例えば2005年の愛知万博では、自動車メーカー各社が電気自動車や燃料電池技術を披露し、来場者に “環境技術の先端企業” という印象を残しました。
これはその後の環境対応車販売の追い風になったと評価されています。
まとめ:浪費か投資か
😏 私
つまり、民間のパビリオンは “コストを投資に変える場” であるわけだ。
浪費ではなく投資。
だが一方で、国のパビリオンはどうだろうか?
ここに妙な温度差があるように思えてならない。
――次回後編に続く。
【大阪万博関連記事】
灼熱の関西万博は日影もなく、パビリオンは長蛇の列、まさに人生の修行の場です。2万歩歩いて何を得た?体験者が語る本音
大阪万博でのカラオケ体験は楽しめるのか?(ドイツ館カラオケ40分のアトラクション)
【後編】万博パビリオンに潜む投資戦略 イメージ戦略とコスト意識(万博の国パビリオン、投資戦略とコスト感覚は本当に適正か?)

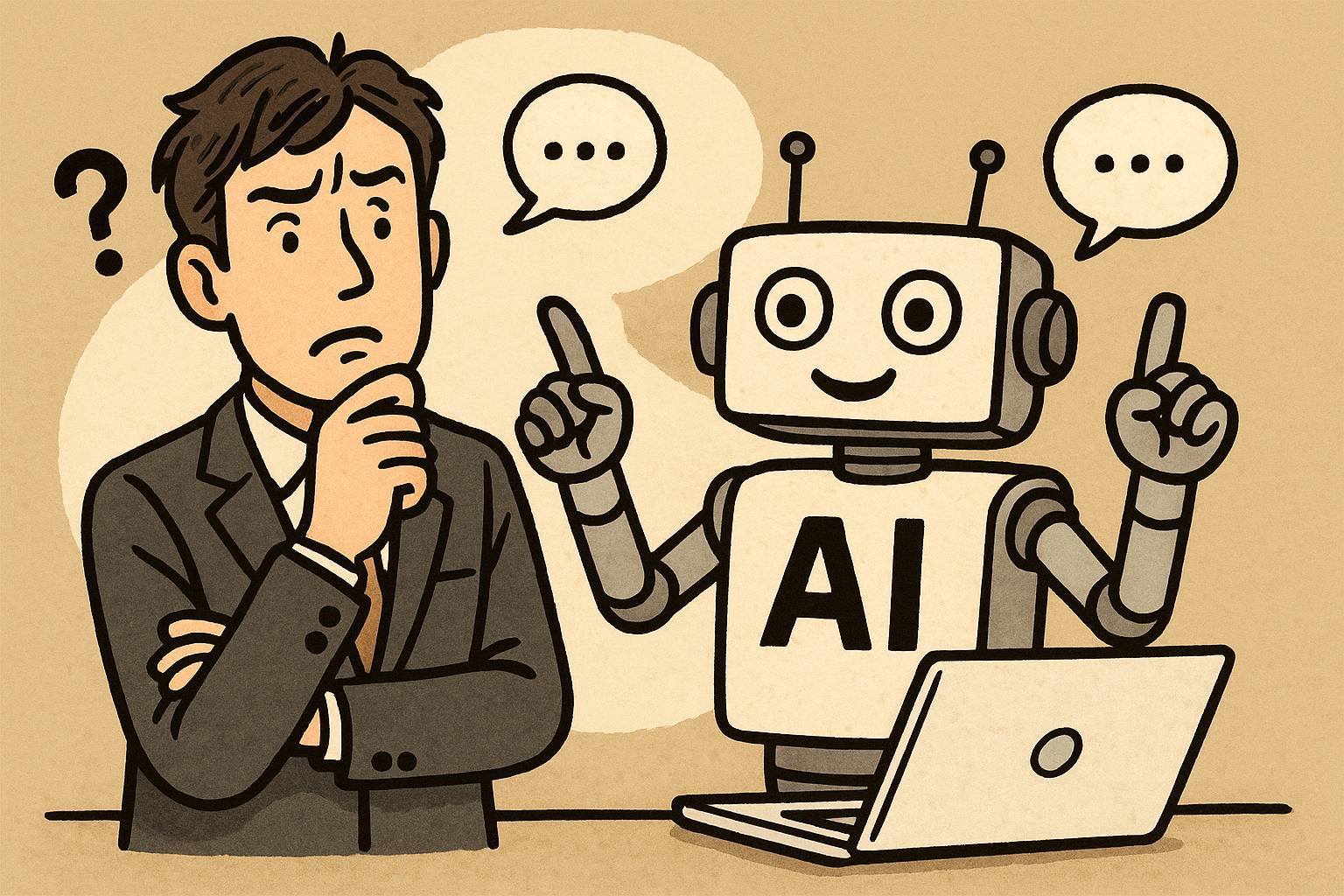
コメント